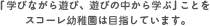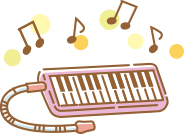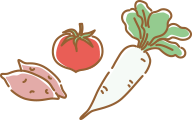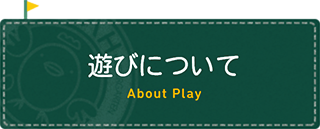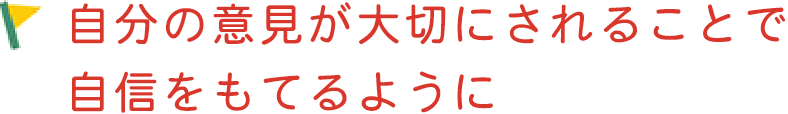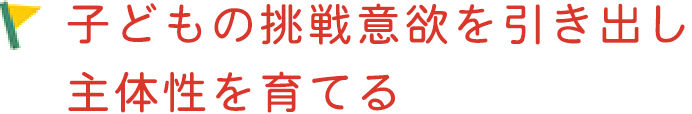先生は、「積み木を高く積み上げてどこまでいけるかな?」「失敗しても何回も挑戦しよう」「もっとこう工夫したら…」というように子ども達の遊びを支え続けます。そうすると子ども達はだんだん自分達なりの遊びのコツをつかみはじめ、やがて遊びに没頭することができるようになります。一人でも、仲間と一緒でも。遊びに没頭する経験を積んでいくことで集中する力がついてきます。そしてそれは「上手にやれた!」「次はもっと楽しく!」といった自信へとつながります。

スコーレの発表会は普段の生活の中で生まれたオリジナルの遊びをどうやってお父さんやお母さんに見てもらいたいか、子ども達がアイディアを出し合って決めます。そうすると子ども達は、自分でものごとを決められるようになっていきます。そして自分の意見が大切にされることを実感し、自分に自信をもてるように。


スコーレの教育はクラス・学年をこえたオープンな異年齢交流。
だから遊びの時間はどこへいって遊んでもいいんです。
入園当初の4~5月はブランコが人気。
3 歳の子は「かわりばんこ」と言っても、まだどうしても自分中心になってしまいます。並んで待っていた子が、自分も早く乗りたいと泣き出しはじめました。
すると隣で乗っていた4歳の子が、さっと降りて「乗っていいよ」と替ってあげます。そして背中を押してあげたのです。乗っている子は本当に嬉しそうでした。
上の子は下の子のお世話をしてあげたい、優しくしてあげたいという気持ちが育ちます。優しくしてもらった子は、今度は下の子に同じように優しくできるようになっていきます。





子どもの挑戦する気持ちを育てるために教師はどう関わるのか?
子ども達と信頼関係をつくりながら、意欲や主体性が育つやり方を工夫していきます。
「今日は大豆をみんなで畑に植えよう」ということではなく、子供の見えるところに大豆を置いておきます。気づいた子ども達に「大豆と言って植えると枝豆になるんだよ」と説明するとみんなで植えることに。
6月に植え、9月に収穫し枝豆を食べました。残りは10月に収穫して大豆に。たくさん収穫できた大豆を子ども達と相談して豆腐を作ることにしました。
子どもの発想に先生はびっくり!「本物の豆腐だ!」と感動しながら食べる子や「牛乳みたいだ!」と豆乳を飲む子、「給食で食べたのを作りたい!」という子ども達は、きゅうりを刻みマヨネーズでおからサラダを作りみんなで美味しく食べました。