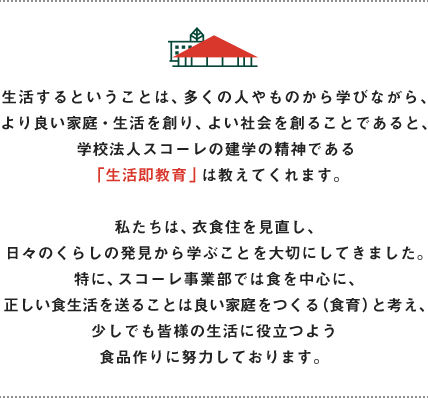

どの家庭でも出来る方法で作る、添加物を使用しない正直な食品。
創立当時、学校の生徒が担当職員と一緒に農産加工を学び、『どの家庭でも出来る方法』をめざしました。工夫を積み重ね、ひとつひとつの商品に心を込めて手作りしてきました。
現在では学園の卒業生が専任職員となり、この製法は受け継がれ守られています。
岩手県盛岡市は西に奥羽山脈、東に北上山地を望む盆地で、自然豊かな場所です。寒暖差の激しい土地柄美味しい農産物がとれます。 その中でも完熟した美味しい農産物をその素材にあった製法でこだわって作っております。自然の味から学び、自然の味を大切にしながら丁寧に加工することで、食材がもつ素の味を生かす手作りの製品になるのです。
「自然のまま・自然の色・自然の味」。添加物等を一切使用せず、一本一本丁寧に手作りして、お客様の元へお届けいたします。





1933(昭和8)年に、「盛岡友の会生活学校」が盛岡友の会会員により立ち上がりました。盛岡友の会会員は、若い母親や女性に対して家庭生活に関する学習の必要性を感じ、羽仁もと子先生のもと自由学園で学んだ吉田幾世
(初代理事長)を代表に推薦しました。
最初に「盛岡友の会生活学校」へ入学した13人の生徒は、羽仁先生の提唱した 「生活即教育」の理念のもと、衣食住、育児、経済生活に関する学習に取り組みました。
生活学校では当時、盛岡では珍しかった洋裁による婦人・子ども服の製作・普及、ケチャップや山ぶどうジュースの販売などの事業も行いました。これが事業部の原点です。「盛岡友の会生活学校」は、農村生活の向上は次世代を担う若い人たちの教育から始めなければならないと痛感し1949(昭和24)年には、各種学校の「盛岡生活学校」として盛岡友の会から独立をはたし、中学を卒業した農家の娘さんの教育に力を入れることにしました。農繁期の協同炊事、季節託児所等の実習も始まり、当時の生徒出身地域をはじめ岩手県下の農村から生活改善に関する相談や講習会の依頼がしきりに持ち込まれるようになりました。


それに応え「働きやすい野良着、農家向きのお料理、漬物、保存食、家庭瓶詰めや大豆利用の研究」等に熱心に取組み、1955(昭和30)年には、全国友の会から委嘱されて「農村生活研究所」が置かれました。
ここでは、自ら畑で栽培した農作物を、栄養価が高い経済的な食品に加工・普及する取り組みが実践され、収益事業部としての活動がここから始まりました。1961(昭和36)年に「盛岡生活学校」は各種学校から高等学校「向中野学園高等学校」になり、収益事業部は向中野学園事業部となり、全国友の会会員・卒業生様への販売を中心にしておりましたが、1988(昭和63)年「全国友の会農村生活研究所」の役割を終え、広く一般の皆様にも販路を拡大していくこととなりました。
 全国友の会農村生活研究所
全国友の会農村生活研究所
年表
| 1933(昭和 8年) | 盛岡友の会生活学校として創立。 |
|---|---|
| 1934(昭和 9年) | 農産加工の授業で、加工食品作りに取り組む。 |
| 1949(昭和24年) | 校名を盛岡生活学校として改称。 |
| 1955(昭和30年) | 盛岡生活学校収益事業部を設置。 全国友の会から委嘱されて 「農村生活研究所」を設置。 |
| 1961(昭和36年) | 法人名を「向中野学園」と改め、向中野学園収益事業部と改称。 |
| 1979(昭和54年) | 向中野学園事業部と改称。 全国友の会農村生活研究所を廃止。 |
| 1988(昭和63年) | 通信販売事業開始。 |
| 1989(平成元年) | ジャム・ジュース等の市内店舗への卸販売開始。 |
| 1990(平成 2年) | パン・菓子・そば製造販売開始。 |
| 1995(平成 7年) | パン・菓子の市内小売店舗への卸販売開始。 |
| 1997(平成 9年) | 事業部棟完成。(農産物加工場・パン工場) |
| 1998(平成10年) | ブルーベリージュースの製造、販売を開始。 |
| 1999(平成11年) | ラ・フランスジャムの販売開始。 |
| 2000(平成12年) | フルーツソースの販売開始。 |
| 2004(平成16年) | 高校敷地内に、スコーレショップ「パタタ」開店。 製品、パンの販売のほか、軽食・ランチの提供及び生徒の実習等も兼ねた飲食店も運営。 ホームページ開設、インターネット通販開始。 市内の郊外型大型店舗・生協とお取引開始。 |
| 2006(平成18年) | 山ぶどうの製品販売開始。 |
| 2008(平成20年) | 委託商品「かりんこ」の販売開始。 |
| 2009(平成21年) | ベリー&ベリージャム・さるなしジャムの販売開始。 |
| 2012(平成24年) | アロニアジャム・白ぶとうジュース・りんごジュースの販売開始。 盛岡スコーレ高校桐花寮・桐輝寮の給食事業開始。 |

